
吉本 翼
Wing社会保険労務士・行政書士事務所代表。大阪で居酒屋・バー・カフェなどの飲食店開業を専門に、開業前の許認可から開業後の労務管理・助成金活用までを一貫支援。食品会社での経験を活かし、実務に即したサポートと経営の見える化を重視している。各分野の専門家とも連携し、「手続きだけで終わらない伴走支援」を提供。初めての開業でも安心して相談できる身近なパートナーとして、飲食業の成長をトータルで支えている。
CONTENTS
[居酒屋・バー・飲食店の許認可業務]
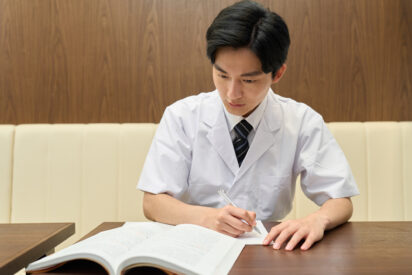
飲食店の営業許可は、店舗の名義が変更になる場合にも新たな対応が必要です。
本記事では、初心者向けに「飲食店営業許可の名義変更」に関する基本知識から、手続きの流れ、注意点、名義変更後のアドバイスまでをわかりやすく解説します。
これから飲食店の引き継ぎや経営変更を考えている方にとって、役立つ情報が満載です。
飲食店を運営するうえで欠かせないのが「営業許可」です。この許可は原則として申請者本人に与えられるものであり、別の人に事業が引き継がれる際には、名義の変更が必要となります。本項では、名義変更の必要性とメリット、具体的に名義変更が必要となるケースについて解説します。
名義変更は、営業許可を適法に維持するために重要です。名義が古いままだと、無許可営業と見なされるリスクが高まります。特に営業を継承するケースでは、許可の主体を正しく引き継ぐことが信頼を維持するためにも不可欠です。名義を新しい所有者に移しておけば、行政対応や書類上のやりとりも明確になり、経営の安定に寄与します。
名義変更が必要となる場面としては、まず飲食店の経営者が変わる場合があります。個人から他人へ、あるいは親族内の引き継ぎなど、事業主体が変わるときには名義変更が必要です。また、個人事業者から法人に移行する「法人成り」の場合も、名義を変更しないと許可が無効と判断される可能性があります。さらに、店舗売却や事業譲渡によって営業を引き継ぐ場合も該当します。ただし、営業所の移転や大幅な施設変更を伴う場合は、名義変更では対応できず、新規許可取得が必要になることもあります。
名義変更を怠ると、許可が無効と判断されるリスクや営業停止の事態を招く可能性があります。変更があった際には必ず保健所に相談し、指示に従って手続きを行うことが重要です。
名義変更という手続きは見落とされがちですが、実務上非常に重要です。許可の主体変更は個別判断となることが多いため、事前に保健所との打ち合わせを行い、必要書類や条件を正確に把握してから手続きを進めてください。

行政書士
吉本翼
名義変更の手続きを始める前に、まず必要書類をそろえることが不可欠です。名義変更に必要な書類は保健所や自治体によって若干異なるため、事前に確認しておく必要があります。一般的に求められる書類には、現在の営業許可証、名義変更用の届出書、新しい名義人の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、店舗の賃貸借契約書や建物賃貸契約書、場合によっては酒類販売許可の証明書(酒類を扱っている場合)が含まれることがあります。
それぞれの書類は有効期限が設定されているものもあるため、発行後に時間が経ちすぎているものをそのまま使わないよう注意します。書類を揃える際には、一通りの書類をコピーして控えを残すようにしておきます。行政書士に依頼して書類作成を任せることも可能ですが、自分で進める場合は不備がないか慎重に内容を確認することが求められます。
また、提出先である保健所の担当窓口をあらかじめ調べておくことも大切です。窓口には受付時間や予約制を採用している場合がありますので、電話での確認や窓口案内を見てから訪問するようにします。
必要書類を準備できたら、申請書類を入手し、記入します。名義変更用の様式には、新規申請とは違う記入欄が設けられていることが多いため、旧許可証や契約情報を見ながら正しく記載することが重要です。
記入が終わったら、準備したすべての書類を申請書に添えて、保健所窓口に提出します。提出時には控えを受け取り、自分の手元にもコピーを残しておくことが望ましいです。保健所によっては提出後に内容確認を求められることがあるため、提出後もフォローできる体制を整えておくとよいでしょう。
保健所窓口での直接提出が基本ですが、最近では自治体によってオンライン申請や郵送での受付を認めているところもありますので、手続き前にその可否を確認しておくべきです。申請後、保健所から追加資料の提出や現地確認が指示される場合もあるため、連絡先を正確に記入し、すぐに応答できるようにしておきましょう。
名義変更の手続きには地域差が大きく出ることがあります。提出書類・様式・窓口対応・審査基準などは保健所ごとに異なるケースが多いため、申請前に管轄保健所と打ち合わせをし、手続き内容を確認したうえで進めることが、後戻りを防ぐ最善策です。

行政書士
吉本翼
飲食店の営業許可において、名義変更は単なる書類手続きではありません。実際には、施設の現状や営業環境が許可基準を満たしているかを再確認されることがあり、その過程で施設検査が行われます。また、名義変更後には新しい営業許可証を受け取る流れになりますが、取得の過程でも注意すべき点がいくつもあります。
名義変更を申請すると、保健所は施設内検査を行って、新しい名義人の店が営業許可の構造・設備基準を満たしているかを直接確認します。検査では、調理場の広さ、手洗い場の設置、換気・排水・清掃設備、厨房と客席間の動線などがチェックされます。自治体によっては衛生設備の細部(床材、天井高さ、水栓仕様など)について個別に定められており、これらが基準を満たさないと許可が下りないか、修正指導を受けるケースがあります。
検査の流れは、名義変更届出書の提出後に保健所から訪問調査の期日が通知され、施設立会いのもと調査が行われます。検査に通らなければ、新許可証の交付が止まるか、差し戻し・再調整を求められることになります。設備を変更していたり前経営者と仕様が異なる場合、より詳細な調査や追加資料を求められることもあります。検査前には施設図面・設備仕様一覧・衛生管理記録などを整理し、保健所の指導担当者と事前相談しておくと安心です。
施設検査をクリアした後、新しい名義の営業許可証が交付されます。受け取りは、名義変更届出と同様に所轄保健所で行われることが通常です。交付までの期間は自治体によって異なりますが、2〜4週間程度が一般的な目安です。ただし申請時期や混雑状況によっては1か月以上かかることもあります。スケジュールには余裕を持っておきましょう。
許可証を受け取る際には、本人確認書類(運転免許証など)の提示が求められる場合があります。場合によっては代理人が受け取る際に委任状が必要となることもあります。また、営業許可証の再発行やオンラインでの交付を認めていない自治体も多いため、指定された方法での受け取りが前提です。
もし検査で不備があったり、書類に誤りが見つかったりすると、名義変更が認められず、新たに営業許可を取得し直す必要になることがあります。その場合、営業停止のリスクが生じるため、一つひとつの手続きを確実に完了させることが重要です。
名義変更を伴う営業許可の移行では、施設検査と許可証交付というプロセスで落とし穴が多くあります。特に、設備仕様の微差異や動線・配管仕様など、保健所の判断が厳しくなるケースがありますので、申請前に保健所の指導担当者と現地確認を行い、検査対応できる状態に整えてから手続きを進めることを強くお勧めします。

行政書士
吉本翼
名義変更が完了したからといって、それで終わりではありません。飲食店を安定して経営し続けるためには、営業許可の維持だけでなく、衛生管理や経営体制の見直しも重要です。特に新しい体制での運営が始まるタイミングでは、細かい見直しが後々のトラブルを防ぐ鍵となります。
まず確認すべきは、名義変更後の営業許可証が正式に交付されているかどうかです。営業を再開する前に、新しい営業許可証が手元にあることを確認し、店舗の見やすい場所に掲示しておくことが、飲食店の信頼性維持につながります。
次に、このタイミングで衛生管理マニュアルを見直すことが不可欠です。食品衛生法や関連基準の改正があれば、以前のルールでは不十分になる可能性があります。最新版の基準に沿う内容に更新し、スタッフ全員がそのマニュアルを理解し、日常業務で実践できるよう研修や掲示資料の整備を行いましょう。
また、新しい経営者に切り替わった場合は、食品衛生責任者の選任、提供内容の変更(酒類提供を含むかどうかなど)、風営法や深夜営業など関連法令の確認も必要です。夜間営業やアルコール提供を伴う業態では、許可以外の法令要件を満たしているか早めにチェックしておくことが大切です。
名義変更を契機に「法人成り(法人化)」を検討することもあります。個人事業から法人に変更することで、税制上の有利性や事業リスク管理の面でメリットが得られます。法人化によって事業資産と個人資産を分離でき、トラブル時の影響を限定できる点は大きな利点です。
また、店舗の譲渡・承継を考える場合、事業譲渡手続きが関係してきます。契約書作成や資産・負債の移転など、引き継ぎに関する法的手続きが必要です。相続による承継の場合も、事業承継制度を把握しておくことが重要です。
これらの手続きに不安がある場合は、行政書士・税理士といった専門家に早く相談することで、スムーズな移行・運営が可能になります。名義変更は単なる形式ではなく、以後の店舗運営を支える転機です。今後の方向性を明確にしたうえで、的確な判断を行うことが、継続・成長の礎になります。
名義変更後は、営業許可の交付だけで満足してしまいがちですが、衛生管理・責任者選任・関連法令の整合性は新体制での運営における要です。特に法人成りや譲渡を絡めるなら、変更後すぐに専門家と確認し、違反リスクのない設計を行うことが成功のカギです。

行政書士
吉本翼
飲食店の営業許可に関する名義変更は、単なる形式的な作業ではなく、法的な遵守と経営の安定を支える重要なプロセスです。名義変更の必要性を理解し、適切なタイミングで手続きを行うことによって、無許可営業といったリスクを回避し、顧客や取引先からの信頼を損なうこともありません。
手続きの流れとしては、事前に必要な書類を揃え、所轄の保健所に提出、施設内検査を経て新たな営業許可証の交付を受ける、という一連の工程を丁寧に進めることが求められます。なお、名義変更の扱いは自治体ごとに細かく異なる場合があるため、各保健所での最新対応状況を事前に確認しておくことが非常に重要です。
さらに、名義変更後の運営においては、営業許可の再確認、食品衛生法に基づく衛生管理マニュアルの見直し、スタッフ教育の強化といった実務面での対応が、継続的な安定経営に直結します。また、法人成りや事業譲渡のような経営戦略の見直しも、このタイミングで合わせて検討すべき重要な要素です。
今回の記事を通じて、飲食店における営業許可の名義変更に関する流れや注意点がより明確になったかと思います。制度の仕組みを理解し、必要な対応を正確に行うことで、あなたの店舗経営はより確実で持続可能なものとなるでしょう。
名義変更の手続きは「届け出るだけ」と思われがちですが、検査対応・衛生管理・経営体制の見直しまで含めて初めて「実務として完了」と言えます。変更のタイミングをきっかけに、全体の体制を一度整えることを強くおすすめします。

行政書士
吉本翼
飲食店営業許可の名義変更に関する基本的な流れや注意点は多くのサイトで説明されていますが、実務現場では名義変更だけで終わらない課題が多数あります。ここでは、「専門家の活用」「リスクマネジメント」「税務と資金調達」の3つの観点から、深く知っておくべきポイントを補足します。
名義変更を自分で進めると、書類の記載ミスや保健所との調整で時間を取られるケースが多くなります。行政書士や弁護士などの専門家を活用することで、書類作成から提出代行、保健所との折衝まで一括して支援を受けられ、ミスを減らすことが可能です。
専門家を選ぶ際には、飲食業界の経験があるか、地元の保健所とのやりとりに強いかを確認します。見積もり提示・契約範囲の明示を初回相談時に行っておくと、後のトラブルを避けやすくなります。実際、名義変更代行は比較的少額になることもあり、安心感と時間の節約という対価を得る選択肢として十分現実的です。
名義変更して新体制で営業を始めた後も、リスクは残ります。たとえば、衛生管理不備による保健所の指導・改善命令、旧経営者との引き継ぎ漏れによる設備仕様の齟齬などです。これらに備えるには、名義変更後のチェックリストを作り、段階的に点検していく体制を整えることが有効です。
また、食品衛生責任者の変更届、軽微な設備変更に対する追加申請、施設構造の一部改修など、細かい届出対応が必要な場面があります。これらを怠ると、次回の保健所検査で指摘されるリスクが高まります。変更後一定期間後に保健所へのフォロー相談を行うことも実務的な手段です。
名義変更は行政手続きの側面だけでなく、経営面にも大きな影響を与えます。特に、個人事業から法人に名義を変えた場合、税務処理や申告方法が変わります。また、補助金や助成金の多くは「法人格であること」を条件にしているケースもあり、名義変更後に申請できなくなる可能性もあります。
加えて、融資契約や取引先・保証人名義の変更が生じた場合、銀行から再審査を求められることがあります。こうしたリスクを軽減するためには、税理士や金融機関担当との早期連携が不可欠です。事前に資金繰り計画や助成制度の条件を確認しながら、名義変更と並行して経営戦略を設計することが望まれます。
名義変更はゴールではなく再出発のステージです。専門家を活用して手続きを正確に進めつつ、変更後の衛生管理体制・税務体制・資金調達ルートを整えておくことが、名義変更を契機とした経営強化の鍵となります。

行政書士
吉本翼
CONTACT
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
以下の地域を中心に対応しておりますが、その他の地域の方もお気軽にご相談ください:
- 大阪府(難波・梅田・天王寺周辺)
- 京都府(河原町・京都市周辺)
- 兵庫県(神戸市周辺)
- 奈良県(奈良市周辺)