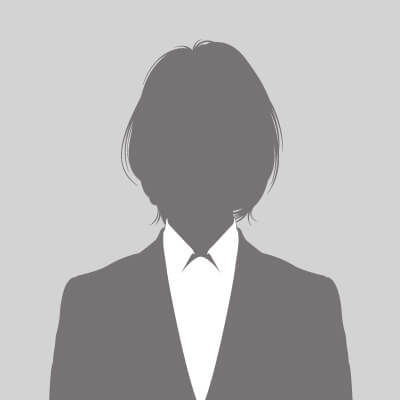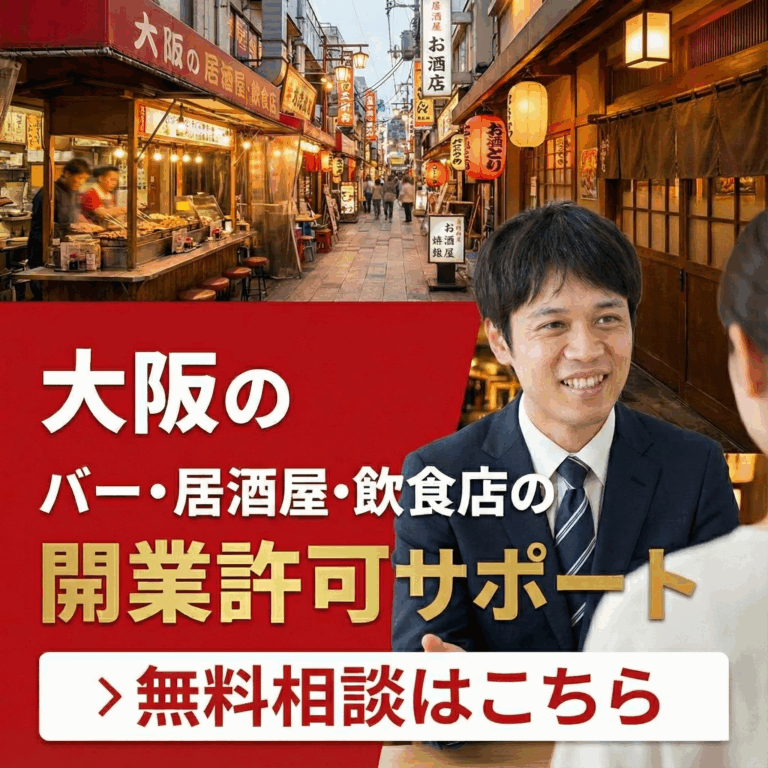※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
大阪市鶴見区の住宅街に位置する商業ビルで、新たにスナックを開業しようとされていたご相談者様は、40代の女性で、長年市内の飲食店で接客に従事されてきた方でした。これまで積み重ねてきた接客経験を活かし、「自分の理想とする落ち着いた空間でお客様を迎えたい」という思いから、独立を決意されたそうです。
開業予定地は、美容系サロンの跡地を活用した約18㎡のテナントで、防音性が高く、間接照明を活かした内装がそのまま使えるという利点がありました。内装設計も「できる限り柔らかい光でリラックスできる空間にしたい」という強いこだわりをもって進められており、開業準備は順調に進行していました。
当初は「飲食店営業許可さえ取れば営業できる」とお考えで、当事務所にもその許可申請の相談としてご連絡いただきました。しかし、店舗の営業スタイルや内装設計をヒアリングする中で、「低照度営業に該当する可能性がある」と判断。風営法に関わるリスクを検証するため、現地での照度測定を提案しました。
結果として、カウンター席の照度は6ルクス、奥のボックス席では3ルクスと、風俗営業2号の対象となる「10ルクス以下」の基準を明確に下回っていました。これにより、ご本人には「飲食店営業許可だけでは営業できない」ことをお伝えし、風俗営業2号許可の同時取得をご提案しました。
行政書士のポイント解説
風俗営業2号とは、「10ルクス以下の照度で飲食を提供する営業」に該当する場合に必要な許可です。多くの方が「風俗営業=接待行為あり」と誤解されていますが、接待の有無にかかわらず、照明条件だけで該当するケースが実は少なくありません。
今回のケースでも、「飲食店営業許可だけで大丈夫」とお考えだったご本人が、照度という観点から風営法に該当することを知り、大変驚かれていました。とくに、スナックやバーといった業態では、演出の一環として間接照明を使うことが多く、気づかないうちに風俗営業の対象になっていることがあります。
行政書士として重要なのは、店舗の営業スタイルや内装計画の段階から法的リスクを見極め、必要な許可を正確に案内できるかどうかです。また、風俗営業許可と飲食店営業許可は、それぞれ所管が警察署と保健所で異なり、審査基準や提出書類も大きく異なります。
今回のご相談では、店舗図面、照度測定報告書、営業方法の詳細な申述書、略図など、すべてを一括で整備。当事務所にて保健所・警察署双方との連携を行い、無駄のないスケジュールで同時進行できたことで、開業希望日に間に合わせることができました。
解決イメージ
照度測定の結果を受け、すぐに風俗営業2号許可の申請準備を開始。スナックの図面を改めて正確に起こし直し、照度配置や設備の説明も含めた詳細な申述書を作成。接待行為が行われない旨を明記し、警察署との事前相談で具体的な説明を重ねました。
鶴見警察署では、特に住宅街に近いエリアであることもあり、照明の調整や防音対策についての説明を求められましたが、初回の相談段階から丁寧に内容を伝えていたため、審査は順調に進行。追加での資料提出も即日対応できたことから、申請から約1ヶ月後には無事に風俗営業2号許可が下りました。
また、飲食店営業許可についても並行して進行し、開業予定日に合わせて両方の許可を取得できました。結果として、ご本人が希望していた「照明を活かした大人の空間で、お客様にゆったりとくつろいでもらえる店」を、法的にも安全な形でスタートすることができました。
現在では、常連のお客様も徐々に増え、「居心地が良い」との声が多く寄せられているそうです。開業前の段階でリスクを察知し、必要な手続きを確実に行ったことが、長く安定して営業を続ける土台になった事例といえるでしょう。