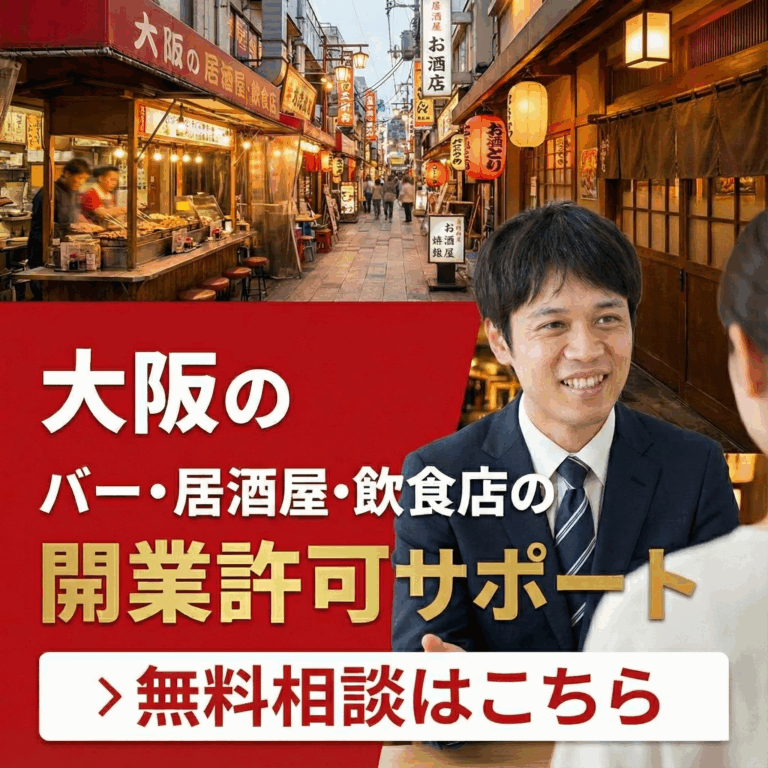※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
ご相談のきっかけは、物件契約前の段階でした。クライアントは新世界エリアにて、木目を基調とした静かなカフェバーを開業したいと考えており、内装デザインの方向性として間接照明を取り入れた低照度空間をイメージされていました。
しかし、現地の内見時に同行した内装業者から「この明るさでは風営法の規制に該当する可能性がある」と指摘され、不安に思われたクライアントが当事務所へご連絡をくださったという経緯です。
まずは現場にて照度を測定したところ、営業室内の平均照度は8.5ルクス。これは風営法上の基準(10ルクス以下)を明確に下回る値であり、風俗営業2号許可の対象になると判断しました。さらに、接待行為やカラオケなどの遊興設備も設けない計画であることから、2号営業の範囲に該当する店舗形態でした。
幸いにも、物件の用途地域は「商業地域」で、100メートル以内に学校や保育施設といった保全対象施設もないことが確認できたため、立地条件としても問題はありませんでした。オープン予定までは約2か月あり、申請スケジュールにもある程度の余裕がある状態でした。
ただし、クライアントが不安に感じていたのは、「飲食店営業許可と風俗営業許可のどちらを先に取るべきか」「同時に進めて問題ないのか」といった流れの部分です。これについては、両許可の制度的な違いを踏まえ、段階的に並行処理する必要がありました。
行政書士のポイント解説
このようなケースでは、まず「飲食店営業許可」と「風俗営業2号許可」の制度上の違いを正しく理解した上で、現実的な申請スケジュールを組み立てることが重要です。どちらの許可も最終的には「図面」に基づいて審査されるため、設計段階で双方の要件を満たしておく必要があります。
今回の店舗では、先行して保健所に提出する図面を元に、厨房の配置・手洗い設備・給排水など飲食店としての構造要件を確定。その上で、照度、扉構造、防音、防犯設備といった風営法上の要件を加味して、同一の図面で両方の審査に対応できるよう調整を行いました。
飲食店営業の構造確認が終わった後は、同時に風俗営業2号許可の申請書類一式を準備。必要書類には、営業所の管理者となるクライアントの身分証明書・登記されていないことの証明書・履歴書・誓約書・写真・平面図・立体図などが含まれます。これらを整えたうえで、浪速警察署と事前協議を実施しました。
協議では、裏口扉に関する自動施錠システムの有無が一つの論点となりましたが、すぐに施工業者と連携し、警察からの指摘に対応可能な構造に変更。2回目の訪問では無事に了承が得られ、本申請へと移行できました。
最終的には、飲食店営業許可が開業予定の約2週間前に交付され、風俗営業2号許可も本申請から約32日で交付されました。これにより、開業日当日から両方の許可に基づいて正式に営業が可能となりました。
こうしたダブル申請の支援には、行政書士の経験と実務感覚が求められます。警察署・保健所・施工業者との連携が鍵となるため、申請人だけで対応するのは難しい場面も多く、専門家のサポートが非常に有効です。
解決イメージ
クライアントは、元々イベント業界で企画や空間演出に携わっており、「人が集まりたくなる場所」を創ることに情熱を持っておられました。そうした背景から、照明を落とし、音楽も控えめで、お酒をゆっくり楽しめる空間を志向されたのだと思います。
その一方で、飲食業は初挑戦ということもあり、法的な許可の種類や流れについては不安が大きかったご様子でした。「風営法」という言葉に驚かれた様子も印象的で、「うちはバーじゃなくてカフェなんですが」と何度か確認を受けたほどです。
しかし実際には、「バーかどうか」ではなく「照度が10ルクスを下回るかどうか」「接待行為があるかどうか」といった具体的な基準によって許可の要否が決まります。その点を丁寧にご説明しながら、許可取得に必要なすべての手続きを一括で対応することで、クライアントも安心して準備に専念できたようでした。
許可取得後も、店内の運営マニュアルや従業員への説明資料の作成など、ソフト面の支援にも取り組みました。こうした「違反を出さない運営体制」の構築こそが、長期的に見てもっとも重要だと考えています。
実際、浪速区周辺では風営法違反による警察の立ち入りや注意指導が増加しており、照度や営業時間に関するチェックが厳しくなっている傾向があります。開業後も継続的なフォローを続けることで、クライアントが安心して経営を続けていけるようサポートしていく予定です。