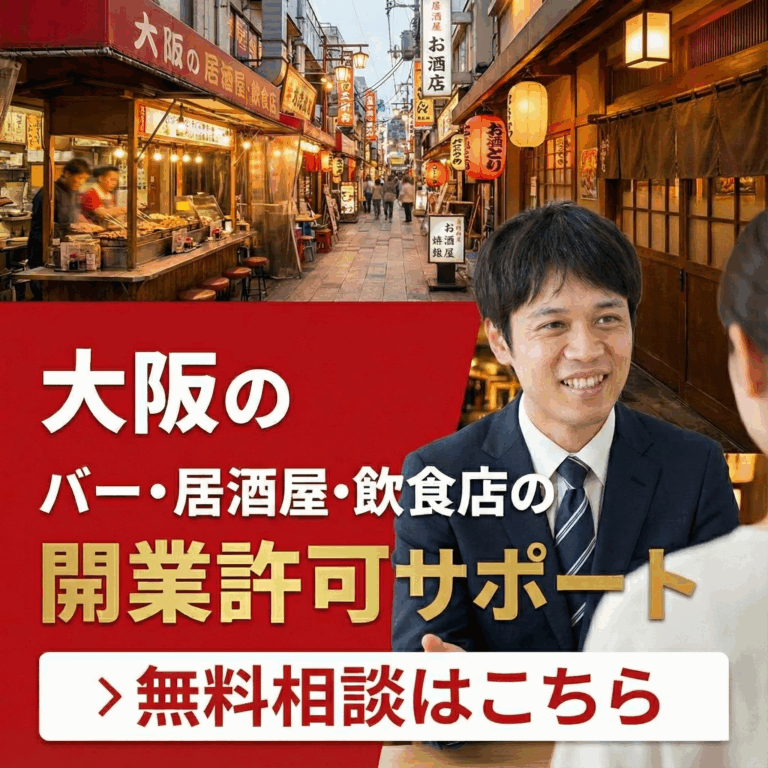※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
今回のご相談は、ある地方に本社を置くWeb開発企業が、過去に業務委託で関わった外国人技術者を正式に正社員として採用したいという意向をもたれたことがきっかけでした。その技術者は、日本の大学院を修了した後、引き続き日本国内での就労を希望しており、双方の希望が一致したことで本格的なビザ申請手続きを検討されることになりました。
企業は地方を拠点にクラウドサービスの開発・提供を行っており、特に若手エンジニアの人材確保が課題でした。その中で、すでにリモート業務での信頼関係が築かれていた候補者の業務理解度・技術力・日本語対応力を高く評価し、ぜひとも正社員として迎えたいと決断されました。
ただし、企業側は外国人雇用もビザ申請も初めての経験であり、「大学での専攻と実務内容の関係性が薄いのではないか」「地方企業でも審査基準を満たせるのか」といった点に大きな不安を抱いておられました。また、必要書類や契約書の整備、報酬や労働条件の基準など、制度的な理解も不十分な状態だったため、ビザ申請手続き全体における専門的な支援を求められて当事務所にご相談いただきました。
行政書士のポイント解説
技術・人文知識・国際業務ビザにおける審査の柱は、本人の学歴と実務内容の関連性、雇用主による適正な雇用体制の整備、そして入管審査に耐えうる証明資料の作成にあります。今回のケースでは、本人がコンピュータサイエンスを専攻して大学院を修了しており、日本語能力試験N2にも合格していることが履歴書や証明書により確認できました。
実務内容としては、クラウドアプリケーションのWeb開発や仕様設計、既存顧客との折衝、要件定義、実装といった業務を予定されており、専攻との関連性は十分に説明可能でした。これらを、具体的な業務フロー図や社内開発体制図を交えて、補足説明資料にまとめることで、専門性と学歴の一貫性を明確に示しました。
企業側には、雇用契約書・賃金台帳・就業規則・源泉徴収票などを依頼し、日本人と同等以上の処遇が保証されていることを入管に対して提示しました。特に報酬面については、月額25万円以上を基本とし、社会保険の適用状況、昇給制度、通勤手当などの待遇面も文書化しました。雇用契約書には職務内容を具体的に記載し、曖昧な表現を避けることで審査通過の可能性を高めました。
また、外国人社員を受け入れる体制として、技術研修プログラムや日本語による社内マニュアル、OJT制度、日本人メンターによる指導体制なども資料化し、外国人が安心して長期に渡って勤務できる環境であることを証明しました。
これら全ての書類を在留資格認定証明書交付申請書に添えて入管に提出したところ、約6週間後に追加書類照会もなく、無事に在留資格「技術・人文知識・国際業務」が認定されました。初めての申請で不安も多かった企業様でしたが、書類の整備と制度への正しい理解により、非常にスムーズな審査通過となりました。
解決イメージ
今回のケースでは、地方の中小IT企業であっても、制度要件を適切に満たすことで外国人技術者を正規雇用することが可能であるということが証明されました。特に本人が大学院で専攻した内容と実際の職務内容が密接に関係していたことが、審査において大きなポイントとなりました。加えて、企業側が必要な労務環境や支援体制を一から整備し、初めての外国人雇用にもかかわらず誠実に対応した姿勢が高く評価されたと考えられます。
ビザ取得後、対象者はエンジニアとして正式に就業を開始し、既存システムの機能改善や利用者からのフィードバック対応、業務効率化のためのツール開発などを積極的に担当されています。企業内部では「技術面だけでなく、異なる視点からの提案が新鮮」との声もあり、社内における多様性の受け入れと意識改革にも繋がっています。
地方都市というハードルを乗り越えてのビザ取得・外国人雇用は、今後の地域産業の持続可能性を考えるうえでも重要な示唆を与えるものです。人材不足が深刻化する中、都市部以外でも優秀な外国人材を適切に迎え入れる環境を整えることで、企業はより柔軟で持続的な組織運営が可能になることを改めて実感できる事例となりました。