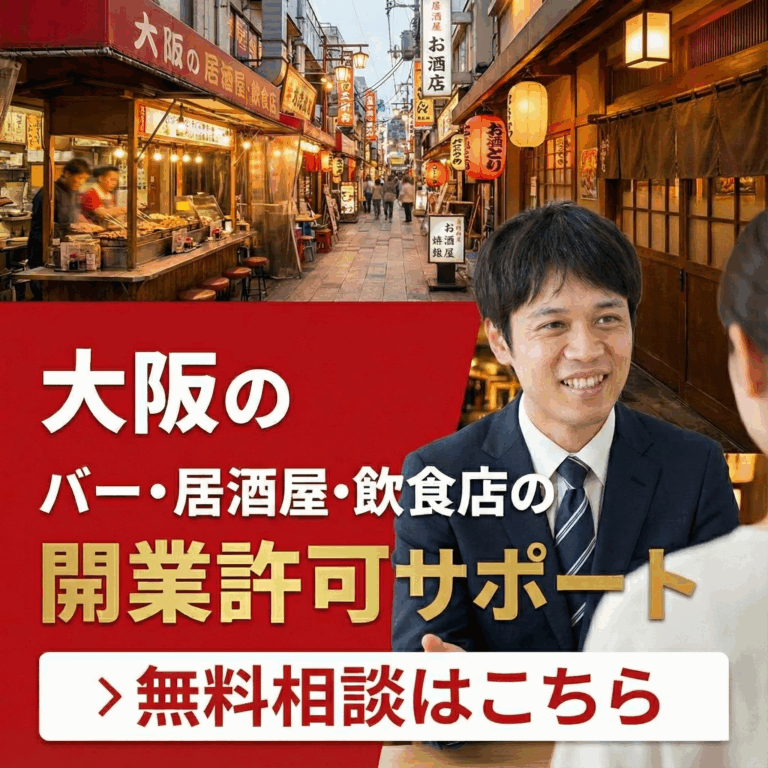※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
今回ご相談いただいたのは、地方の山間部で長年にわたり地元の人々に親しまれてきた田舎料理店を経営されている60代の女性店主様でした。お店では、自らの人脈で仕入れた地元産の野菜や、猟師から直接手に入れる猪肉などを使い、煮込み料理や家庭的な郷土料理を提供されており、休日には観光客も多く訪れる人気店として知られていました。
しかし近年は、地域の高齢化や若者の都市部流出の影響から、店舗の運営を支える従業員の確保が難しくなっていました。特にコロナ禍以降は、アルバイトも安定して雇えず、営業自体に不安を感じるような状況が続いていたそうです。そんな中、知人の紹介で出会った元技能実習生のベトナム人男性に好感を抱き、「この人にぜひうちで働いてもらいたい」という気持ちが強くなり、外国人雇用に踏み切る決意をされました。
しかしながら、「ビザの取得は個人経営の飲食店には難しいのではないか」「そもそも制度がよく分からない」という不安も大きく、地域の行政窓口を通じて当事務所にご相談いただきました。
行政書士のポイント解説
今回の申請は、特定技能(外食業)への在留資格変更であり、外国人本人の資格要件と、受け入れ側である飲食店の制度的な整備の両面を丁寧に整える必要がありました。
まず外国人側の要件としては、申請者であるベトナム人男性がすでに食品製造分野で3年間の技能実習を修了しており、特定技能評価試験(外食業)にも合格していたため、在留資格上の条件はすでに整っていました。技能実習から特定技能への移行は、経験がある分スムーズですが、その分だけ受け入れ側の責任や制度遵守も厳しく問われます。
個人経営の飲食店であっても、雇用契約書・出勤簿・賃金台帳・労働条件通知書・就業規則・36協定書といった書類の整備、社会保険・労働保険の加入状況、そして継続的な監督体制と日本語での生活支援体制の確保が求められます。店主様は非常に真摯に対応されており、帳簿や勤怠記録のデジタル化にも積極的に取り組まれました。
地方での勤務という点では、「実在性」「業務の継続性」「就業環境の安定性」を証明するために、店舗の外観・内装の写真、仕入れ先との過去の取引実績、営業時間ごとのオペレーションフロー、過去3年間の売上推移、厨房の安全管理マニュアルなど、あらゆる角度から補強資料を用意しました。
また、監督者として働く店主様ご自身の経歴や指導経験、衛生管理資格の保有状況についても詳細に説明し、登録支援機関を活用した生活支援の内容(相談体制、日本語教育の手配、定期的なモニタリング)も申請書に反映させました。結果的に、書類提出から約2か月後に在留資格変更が許可され、無事に在留カードも発行されました。
解決イメージ
正直、外国人の方を雇うなんて考えたこともありませんでした。ましてやうちは小さな田舎の料理屋ですし、手続きなんてテレビや新聞の中の話だと思っていました。でも、知人から紹介された彼は本当に真面目で、一緒に働いてみたいと思える人でした。厨房の手際もよく、お客さんへの挨拶も丁寧で、「この人なら」と直感したんです。
でもやっぱり、ビザの話になると不安だらけでした。パソコンも苦手だし、役所のことなんて何をどう調べたらいいかも分かりません。そんな中で行政書士の先生にお願いしてからは、ほんとうに一つ一つ丁寧に教えていただいて、資料の準備も手伝ってもらいながら、なんとかやってこれました。
特にありがたかったのは、彼が安心して働ける環境を一緒に考えてくださったことです。今では厨房を任せても大丈夫なくらいになってくれて、お客さんからも好評です。何より、うちの店のことを「海外にも紹介したい」と言ってくれたのが嬉しくて、こんなふうに思ってくれる若い人がいてくれるだけで、本当に励みになります。これからも一緒に頑張っていけたらと思っています。ありがとうございました。