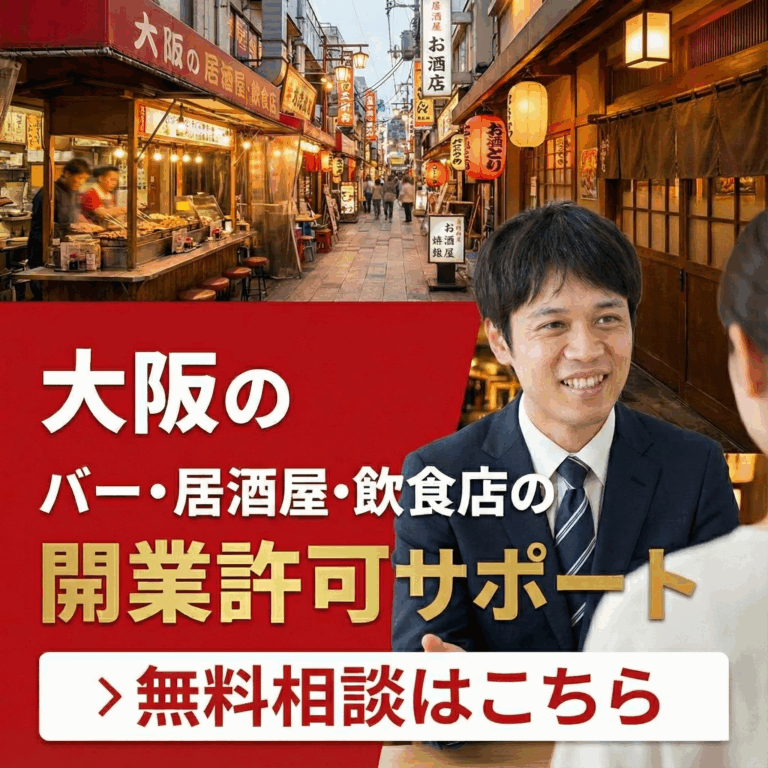※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
ご依頼者様は、大学卒業後から約10年間、就労継続支援B型事業所に勤務されており、障がいのある方が働くことの意味やその大切さを現場で日々感じておられました。ところが、制度に縛られた中での支援や、職員の入れ替わりの激しさに違和感を抱くようになり、「もっと利用者目線の場を自分でつくれないか」という思いから独立開業を決意されました。
摂津市は地域密着型の福祉施策が充実している一方、民間ベースで障がい者の就労と地域交流を融合させたようなスペースはまだ少なく、「カフェを軸に就労訓練と地域コミュニティの橋渡しができる場」にニーズを感じていたとのことでした。
しかし、現実問題としては店舗物件の取得や厨房設備の導入、什器類の購入、さらにスタッフの人件費を支払うまでの運転資金など、開業資金は相当額に上る見込みで、ご本人の自己資金だけではとても足りない状況でした。そこで創業融資を利用して立ち上げたいとのことで、インターネット検索を通じて当事務所にご相談いただきました。
担当行政書士のコメント
このケースでは、「収益性と社会的意義の両立」というテーマをいかに創業計画に落とし込むかが鍵でした。単なる飲食店とは異なり、障がい者支援を行うカフェの場合、売上面や業務効率で懸念を抱かれることも少なくありません。そのため、支援の現場で積んできたご経験や、スタッフ体制、作業内容の具体性を織り交ぜながら、事業の実行力・継続性を丁寧に示していくことが必要でした。
まず、計画書では対象顧客を「障がいのある若年層」と「地域の高齢者」に設定し、支援対象者には軽作業や接客補助を段階的に任せながら、来店客にはゆっくり過ごせるカフェ空間を提供するという仕組みを説明しました。また、地元の福祉事業所との連携予定や、行政機関への協力申請などのアプローチも加えることで、事業としての信頼性を高めました。
資金使途としては、厨房機器や冷蔵庫、業務用コーヒーマシンなどの設備費を中心に、店内のバリアフリー改装費、ホームページ作成費、チラシ印刷・ポスティング費用などを計上。必要資金は約480万円、そのうち自己資金150万円、創業融資で330万円を調達する形で日本政策金融公庫へ申し込みました。
事前面談の対策としては、質問想定に基づいた練習を繰り返し、ご自身のビジョンを的確に伝える言葉の選び方や、資金使途の正当性を裏付ける資料(見積書、取引予定先一覧など)の整備も支援しました。その結果、申請後2週間ほどで希望通りの融資が決定。開業準備を加速させることができました。
現在は、地域の民生委員や福祉関係者も協力しながら、カフェの常連客も徐々に増えてきています。利用者にとっても、ただの訓練ではない「社会とつながる場所」としての存在となっており、創業の意義が着実に形になりつつある実感を得ています。
お客様の声
自分がずっと現場で感じてきた課題に対して、何らかのかたちでアクションを起こしたいと思っていました。でも、資金面の不安や「本当に自分でやって大丈夫なのか?」という気持ちもあり、何度も踏みとどまりかけました。
そんなときに相談した行政書士の先生が、ただ融資の書類を手伝ってくれるだけでなく、私のビジョンや不安にも丁寧に寄り添ってくださったことが、今回の創業の大きな支えとなりました。自分ひとりではとてもここまで考えられなかったですし、計画書が採択されたときには「やっと一歩踏み出せた」と涙が出ました。
融資で調達できたおかげで、物件契約から内装工事、厨房機器の購入までスムーズに進められました。開業してまだ間もないですが、利用者の方やご家族から「ありがとう」と言っていただくことも増え、この場所の意味が少しずつ伝わっているように感じます。これからも地域の方と一緒に、ゆっくりと育てていけるカフェにしていきたいです。