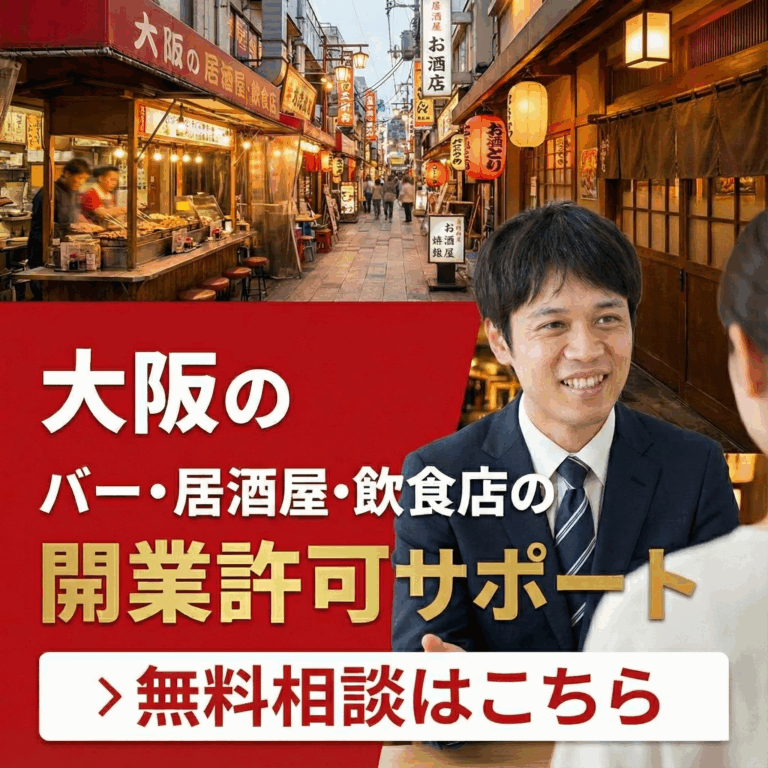※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
N社は、大阪市中央区で創業40年を超える老舗和食料理店で、地元の常連客から観光客まで幅広く来店する人気店です。料理の味はもちろん、伝統的な和の雰囲気と丁寧な接客で知られており、近年はSNSやグルメアプリを通じた外国人観光客の集客にも力を入れてきました。
今回、特定技能ビザでの就労対象となったTさんは、かつて同社が受入機関となり、技能実習制度を通じて3年間勤務していたミャンマー人男性です。実習修了後は帰国したものの、母国で再就職した現場があわず、再び日本で働きたいとの希望を持っていました。
Tさんは技能実習中、主に調理場の補助として野菜の下処理や盛り付け、仕込みなどを担当し、まじめで器用な仕事ぶりから社員や板前からの信頼も厚い存在でした。帰国後も定期的に連絡が続いており、今回、特定技能試験と日本語試験の合格を報告するとともに、「また同じ店で働きたい」という強い希望を伝えてきたため、N社としても再雇用を検討。制度的に対応可能かどうかを確認する目的で、当事務所へご相談をいただきました。
担当行政書士のコメント
本件は、技能実習制度を修了した外国人材が、同業種内で再就労を希望するケースであり、制度上は特定技能ビザが最適な選択肢となります。ただし、制度上の仕組みを正確に理解し、受入企業として必要な準備ができていることを、書類上でしっかり示す必要があります。
まず、Tさんが受験・合格した「外食業分野の技能測定試験」と「日本語試験(JFT-Basic)」の合格証明書を取得し、特定技能ビザの申請要件を形式的に満たしていることを確認しました。次に、技能実習期間中の実績や職務内容を振り返り、同社での再就労に合理性があることを、過去の評価書や写真、業務記録を用いて裏付けました。
企業側の義務として重要なのは、「支援計画書」の作成です。今回は、N社が初めて特定技能制度を利用することから、支援責任者・支援担当者の選任、外国人との日常的な連絡手段の確保、生活支援の内容(住居の手配、行政手続きの同行、相談窓口の確保など)を1つずつ確認しながら、実行可能な計画に落とし込みました。形式的に整っただけの支援計画ではなく、Tさんの状況に即した「実行性のある支援体制」として、実際の支援担当者の名前・役割・支援頻度などを具体的に記載しました。
さらに、雇用契約についても、業務内容・労働時間・賃金・福利厚生などについて、日本人社員と同等以上であることを明記した契約書と労働条件通知書を添付。技能実習時代と比較して賃金条件が向上していることも、職業キャリアの継続性として評価されるポイントとなります。
書類提出後、審査期間は約6週間。特に大きな補正もなく、在留資格認定証明書が交付されました。Tさんは母国から再来日し、現在は再びN社の厨房で活躍しています。調理技術にさらに磨きがかかり、同僚からも「帰ってきてくれて助かった」と喜ばれています。
お客様の声
Tさんはもともととてもまじめで、調理場の仕事も丁寧にこなしてくれていたので、技能実習が終わって帰国する際は正直とても残念でした。でも、その後も連絡をくれて、「また日本で働きたい」と言ってくれたときは、うれしさと同時に「制度的に可能なのか」という疑問も正直ありました。
特定技能という言葉自体は知っていましたが、実際にどういう書類が必要で、どんな支援が求められるのかまでは分かっていなかったので、今回専門の行政書士の先生にお願いすることにしました。
相談の段階から、制度の概要、会社としての責任、必要な準備などを丁寧に教えてもらえたのが大変助かりました。特に支援計画については、実際の業務とのすり合わせをしながら現実的な内容を一緒に考えてもらい、「これなら本当に支援できる」という感覚を持てたことが大きかったです。
無事にTさんのビザが認定され、再来日してくれたときは、社員全員が拍手で迎えました。日本語もさらに上手になっていて、以前よりも自信を持って働いている姿を見て、今回の申請に本気で取り組んでよかったと思っています。今後も必要があれば、特定技能制度を活用していきたいと考えています。本当にありがとうございました。