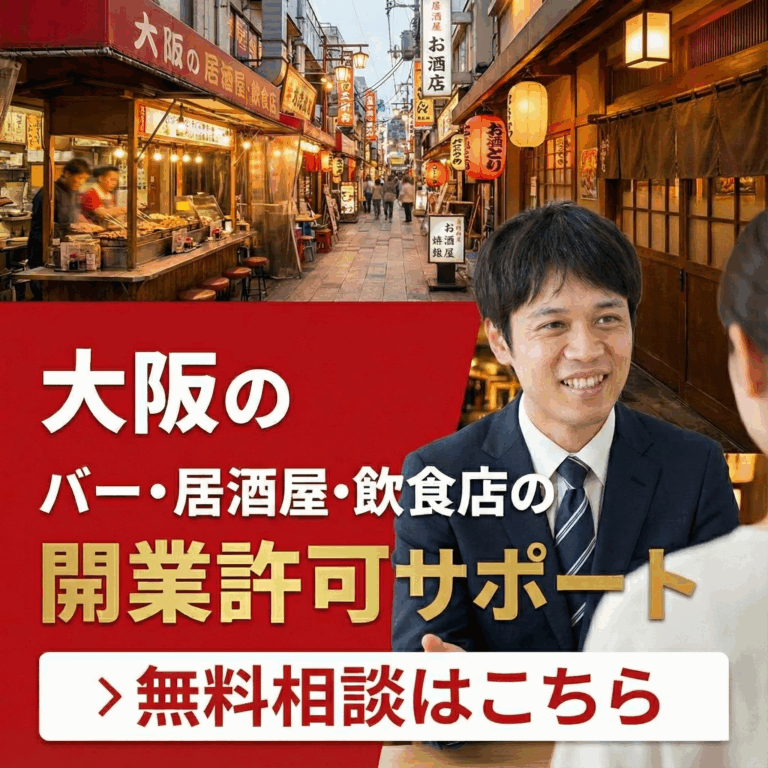※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
T様は台湾出身で、約6年前に「技術・人文知識・国際業務」ビザにより来日し、大阪市内の食品輸出会社で貿易業務を担当していました。日本全国の酒蔵から地酒を仕入れ、台湾・香港を中心に輸出する業務に携わる中で、日本酒の奥深さと文化的価値に魅了され、「いつか自分で日本酒を提供する場を持ちたい」という夢を抱くようになったそうです。
5年間の勤務を経て退職後、貯金と家族からの支援をもとに、経営管理ビザで日本酒バーを開業する決意を固めました。場所は、飲食業の競争が激しい大阪市北区。とくに梅田エリア周辺は飲食店舗の入れ替わりも多く、立地選びやコンセプト設計が重要です。T様は「日本酒に特化した静かなバー」という明確な業態で差別化を図ろうとされており、その実現に向けて当事務所にご相談くださいました。
担当行政書士のコメント
経営管理ビザの審査で最も重視されるのは、「事業の実現可能性」「継続性」「収益性」の3要素です。本件では、T様が業界での実務経験があるとはいえ、飲食店の経営自体は初めてであり、ビザ取得には説得力ある事業計画書と具体的な準備資料が不可欠でした。
まず、物件の確保については、北区中津にある元ワインバーの居抜き物件を契約されており、開業までのスケジュール感も具体的でした。内装はほぼ現状のまま使用でき、厨房機器も揃っていたため、初期コストを抑えた開業が可能である点をアピール材料としました。物件に関しては、賃貸借契約書、店舗内外の写真、レイアウト図面なども添付して「営業開始に向けた準備が実在すること」を証明しました。
次に、事業計画書では「地酒と和風つまみ」「カウンター8席」「客単価4,000円前後」「週5日営業」「SNS集客重視」といった明確な営業方針を打ち出しました。特に、台湾人・香港人観光客をターゲットにしたインバウンド戦略を加えることで、日本酒の輸出業務に携わっていた経験を活かした独自性を持たせました。
また、開業時に提供する酒の銘柄や仕入れ先リスト、試作メニュー、収支予測表、仕入れ・人件費の内訳も作成し、売上の根拠を数字で示しました。補足資料として、日本酒の講習受講歴や、利酒師資格の取得予定なども記載し、専門性の高さと継続意欲の強さを裏付けました。
申請書類一式を揃えたのち、大阪出入国在留管理局へ在留資格変更申請を行い、約5週間で許可が下りました。開業はその翌月に無事実現し、T様の夢であった日本酒バーが北区でスタートを切ることができました。
お客様の声
私は以前、日本で働いていたときに日本酒の魅力を知り、自分の国の人たちにももっと紹介したいと思いました。仕事を辞めてから、何度も「日本で日本酒バーを開こう」と考えましたが、ビザの問題が一番不安でした。
日本語はある程度話せても、法律や制度のことはとても難しく、特に「経営管理ビザ」という名前すら初めて聞くような状態で、何から始めればいいか分かりませんでした。そんな時、ネットで調べて行政書士の先生に相談しました。
初回の相談では、開業の流れ、必要な書類、ビザの審査ポイントをとても丁寧に説明してくれて、私がやるべき準備が明確になりました。特に、事業計画書の部分では「お客様にどう説明すれば伝わるか」を一緒に考えてくれて、日本語が不安な部分もフォローしていただきました。
無事にビザが下りて、いまは梅田の静かな通りに小さな日本酒バーをオープンできました。最初のお客様は偶然通りかかった台湾の観光客でした。自分の作った空間で、日本の酒を出せることがとても嬉しいです。これからもっと店を広げて、たくさんの人に日本酒を楽しんでもらいたいと思っています。今回のサポートには本当に感謝しています。