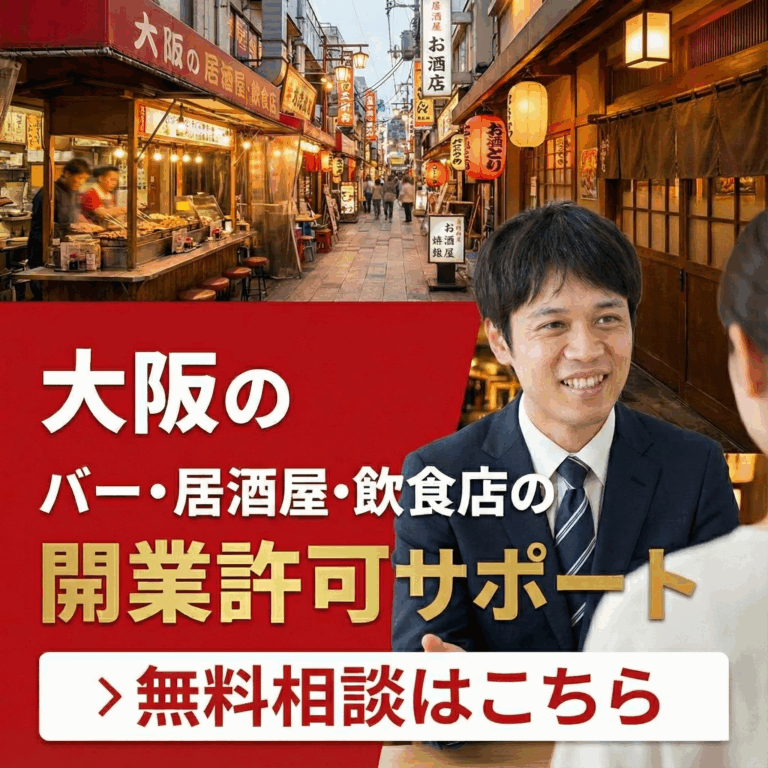※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
H社は、大阪市北区を拠点に複数のビジネスホテルを運営している企業で、外国人観光客やビジネス利用客を多く受け入れてきました。清掃・ベッドメイキング・共用部分の整備などを担当する現場の人材については、かねてより技能実習制度を活用し、主に東南アジア諸国から若手人材を育成してきました。
今回、再雇用の対象となったSさんは、約3年前に技能実習生としてH社に配属され、3年間にわたって複数のホテル現場で勤務してきたネパール人男性です。日本語でのやりとりも支障がなく、責任感のある業務姿勢から、日本人従業員からの信頼も厚く、実習期間満了後の帰国時には惜しまれながらの別れとなりました。
その後、Sさんはネパールで生活を再建しながらも、「日本で再び働きたい」という強い希望を持ち、特定技能制度の存在を知ったことから、技能試験と日本語試験に合格。その結果をもって、かつての受入企業であるH社に再就職の希望を伝えたことで、今回の案件が動き出しました。
ただし、H社では特定技能制度を利用した受入れが初めてだったため、制度理解や支援体制の整備に不安があり、専門家による申請サポートを希望されて、当事務所へご依頼いただきました。
担当行政書士のコメント
特定技能制度においては、技能実習の修了経験がある外国人が、同一の業種分野に再就職できる道が開かれています。ただし、形式的にはまったく新たな在留資格を取得することになるため、書類の準備は非常に重要であり、特に雇用企業側の「外国人支援体制」が問われることになります。
本件では、Sさんが過去にH社で技能実習生として働いていた実績があるため、再受入れの適性については十分な裏付けがありました。課題は、H社側が特定技能の制度要件を初めて扱う点であり、支援計画書や受入体制整備についてのノウハウが不足していたことです。
まず、支援計画書の策定では、Sさんの生活支援・職場支援の両面をカバーした内容を設計しました。日本到着後の空港出迎え、区役所での住民登録・健康保険手続きへの同行、日本語学習支援、生活ガイダンスの提供、定期的な面談・相談対応などを、年間スケジュールとして具体的に記載しました。これにより、単なる「支援義務の形式的履行」ではなく、「実効性ある支援体制」であることをアピールしました。
加えて、Sさんが業務に即応可能な人材であることを示すため、過去の技能実習評価書や、現場リーダーの推薦コメントを補足資料として提出しました。H社としても、彼の丁寧な清掃技術や作業スピード、日本人スタッフとの円滑なコミュニケーション能力を高く評価しており、その内容が審査官にも伝わるよう、定量的・定性的な表現を盛り込みました。
企業としての安定性や労働環境面でも、同一職種の日本人スタッフと同条件で雇用契約を結んでいること、社会保険加入や36協定の届出状況などを客観的な書類で示し、「適正な雇用・適切な管理体制」が整っていることを強調しました。
その結果、審査開始から約6週間で在留資格認定証明書が交付され、Sさんはネパールから再び来日。H社のホテル清掃現場において、即戦力として業務に従事しています。
お客様の声
以前、技能実習生としてSさんに3年間働いてもらっていたときから、「この人は本当にまじめで信頼できる」と感じていました。実習満了で帰国されたときは現場のスタッフ全員が「また戻ってきてほしい」と話していたほどです。
そんなSさんから「もう一度働きたい」という連絡をもらったとき、すぐに受け入れたいと思ったのですが、特定技能という制度についてはまったく知識がありませんでした。特に「支援計画を作らないといけない」「生活支援の内容も具体的に説明する必要がある」と聞いて、不安が大きくなり、専門家のサポートを探すことにしました。
今回お願いした行政書士の先生には、書類の準備から支援計画の作成、会社としてどのように対応すべきかまで、非常に分かりやすく丁寧に説明していただき、本当に助かりました。書類だけでなく、会社としての姿勢や考え方まで伝えることが大事だということを実感しました。
無事にビザが下りて、Sさんがまた戻ってきてくれたときは、現場全体が本当に喜んでいました。これからも、こうした制度を上手に活用していきたいと思います。このたびは本当にありがとうございました。