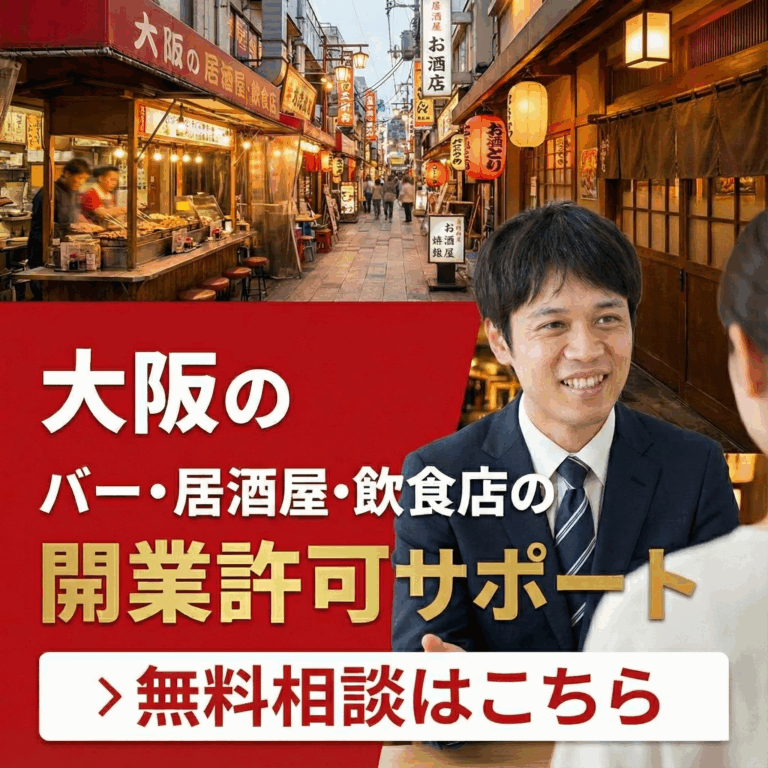※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
M社は大阪市平野区に本社を構える老舗の食品製造会社で、冷凍食品や惣菜の加工・包装を主業としています。長年にわたり技能実習制度を活用し、主にフィリピン人やベトナム人の若手人材を育成してきました。なかでもM社の従業員から高く評価されていたのが、技能実習生として3年間勤務していたフィリピン人のGさんでした。
Gさんは、実習期間中から業務への責任感が強く、清潔管理・加熱工程・パッケージングなど複数の工程を的確にこなし、現場の日本人スタッフからも「また戻ってきてほしい」との声が上がるほどの存在でした。実習期間終了後にフィリピンへ帰国したGさんは、その後も日本での再就職を強く希望し、M社へ再雇用の打診を行いました。
M社としても、慢性的な人手不足を補ううえで即戦力となるGさんを迎え入れたいと考え、特定技能制度による受入れを決定。しかし、制度上の支援義務や必要書類の整備が煩雑で、「社内で申請を進めるには限界がある」と判断し、当事務所に申請代行をご依頼いただくこととなりました。
担当行政書士のコメント
特定技能ビザは制度設計上、単純な「延長」や「切替」ではなく、新たな在留資格としての審査が行われます。したがって、企業側と外国人本人の双方が、制度の趣旨を正しく理解し、かつ必要書類や支援体制を整えなければなりません。
今回の案件では、Gさんが技能評価試験と日本語能力試験にすでに合格していたため、本人要件はクリアしていました。問題は、受入れ企業であるM社側の支援体制の構築でした。特定技能では、外国人が安心して生活・労働できるよう、企業が生活支援・職場支援を義務付けられており、詳細な「支援計画書」を策定する必要があります。
支援計画の作成では、Gさんが以前在籍していた実績を活かし、支援内容が形骸化しないよう、以下の点を重視しました。具体的には、日本到着時の空港送迎・役所手続きへの同行・生活オリエンテーションの実施・銀行口座開設支援・日本語学習支援・定期面談などを、1年間の支援スケジュールに落とし込み、現実的かつ実効性のある計画にまとめました。
また、企業としての雇用体制や給与水準についても、外国人が日本人と同等の待遇であることを証明するために、労働条件通知書・就業規則・労使協定などを補完資料として提出しました。特に、同職種の日本人社員と同等の月収を確保できている点が、審査上大きな安心材料となりました。
さらに、過去にGさんが技能実習中に取り組んだ業務の評価書や、現場責任者による推薦文なども資料として添付。これにより、Gさんの適性が既に確認済みであることを具体的に示し、在留資格認定証明書の発行を目指しました。
結果、約5週間の審査期間を経て、在留資格認定証明書が無事交付され、Gさんはフィリピンからの再入国を果たし、再びM社の一員として業務に就いています。
お客様の声
弊社ではこれまで多くの技能実習生を受け入れてきましたが、特定技能での受け入れは今回が初めての経験でした。Gさんの実習期間中の働きぶりは非常に素晴らしく、彼女の帰国後も「もう一度戻ってきてほしい」と社員たちから声が上がっていたほどです。
しかし、実際に特定技能での再雇用を進めようとした際、申請の複雑さや支援義務の重さに戸惑い、社内だけでの対応は困難と判断して専門家に依頼することにしました。結果的に、申請業務はもちろん、支援体制の構築や書類作成についても一つひとつ丁寧にサポートしていただき、非常にスムーズに進めることができました。
支援計画書の作成では、我々の現場に合った現実的な方法を一緒に考えていただけたことがとても助かりましたし、審査官にとっても納得しやすい資料を整えてくださったと感じています。Gさんが再び弊社で働いてくれることになり、現場にも活気が戻ってきました。
今後も特定技能制度を活用する場面が出てくると思いますので、引き続きお世話になりたいと思います。このたびは本当にありがとうございました。