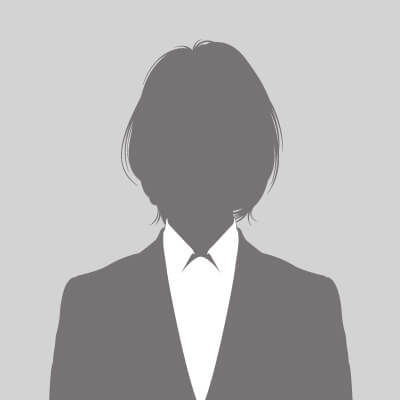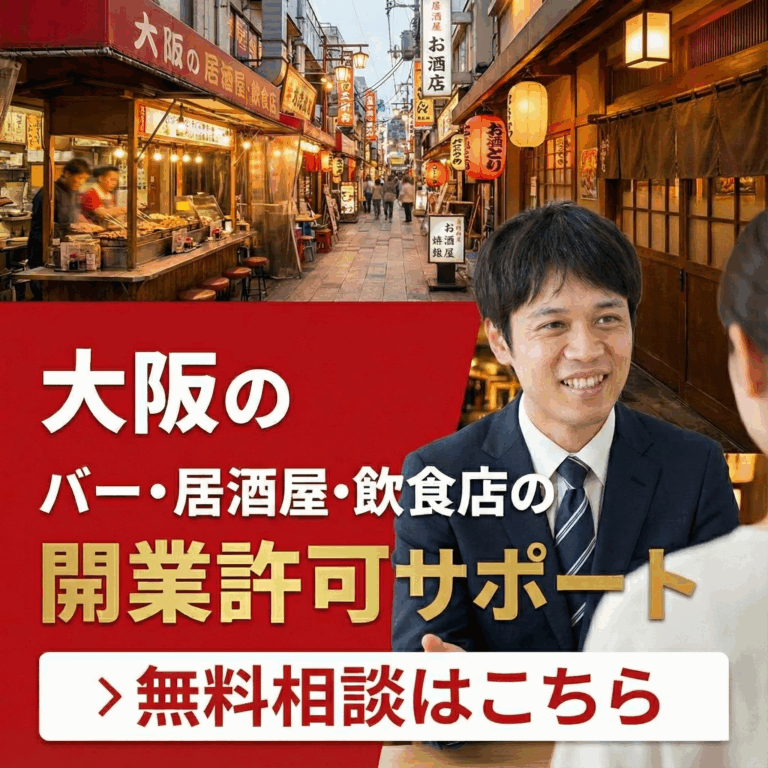※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
大阪市住吉区で複数の高齢者施設を運営しているK法人様からのご相談でした。3年前にフィリピンから受け入れた技能実習生であるAさんが、実習2号を良好に修了し、帰国後もフィリピン国内の介護施設で就労を続けていたという状況でした。Aさんの働きぶりや人柄は高く評価されており、法人側としては「また戻ってきてほしい」という強い要望を持っておられました。
一方で、制度が技能実習から特定技能へと切り替わっていたため、「どのように申請を進めればよいのか」「現地にいるAさんと連絡を取りながらどこまで準備できるのか」といった具体的な運用方法が分からず、当事務所にご相談いただいたのがきっかけです。
初回のヒアリングでは、Aさんの実習修了状況、日本語能力、介護に関する就労経験、そして特定技能の試験要件の確認から着手しました。幸いにもAさんは実習2号修了後であったため、技能試験・日本語試験ともに免除対象であり、在留資格認定証明書交付申請での対応が可能でした。
担当行政書士のコメント
特定技能ビザの申請は、制度上「即戦力」であることが前提となっているため、技能実習修了者がそのままスライドする形で特定技能へ移行するのは、非常に合理的かつ有効なルートです。ただし、その際に求められるのは、雇用する企業側が十分な支援体制を整え、それを「文書化」して提出できるかどうかです。
今回のケースでは、K法人様は技能実習制度には慣れていたものの、特定技能制度での受入れは初めてのケースでした。まず、支援計画の策定が必要となり、生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談窓口の設置、転職防止のための定期面談などを、企業の実情に合わせて設計しました。
また、フィリピン現地のAさんとのコミュニケーションは主にLINEとZoomを活用し、必要書類(パスポート、在職証明、住民登録情報など)を逐次取り寄せながら、本人の希望や状況に即した形で申請書を構成しました。
法人側については、雇用契約書、労働条件通知書、事業所情報、就業規則の一部抜粋などを整え、支援責任者や日本語支援担当者の選任、外部相談窓口の連絡体制も明文化して提出しました。さらに、過去の技能実習時の勤務状況を説明する書類や、当時の担当者による推薦文も添付し、在留管理庁に対して「本人が即戦力であり、受入体制も十分である」ことを一貫して伝える構成を取りました。
その結果、申請から約2か月で在留資格認定証明書が交付され、フィリピン国内の大使館手続を経て、Aさんは無事に再来日。現在は大阪市住吉区の同じ施設で、以前と変わらぬ笑顔と責任感で業務に従事されており、現場の雰囲気にも再び活気が戻っています。
お客様の声
Aさんは本当に大切な存在でした。実習中も一度も遅刻せず、丁寧で真面目な働きぶりにスタッフ一同が信頼を寄せていました。実習が終わって帰国されたときには寂しい思いをしましたが、「また戻って働きたい」という本人の希望を聞いて、何とか制度を使って迎え入れたいと思いました。
とはいえ、特定技能という制度は初めてで、正直まったく分からないことばかりでした。そんな中で行政書士の先生にお願いしたことで、制度の仕組みを丁寧に教えてもらいながら、必要な手続きをすべてリードしていただけたのは本当に助かりました。
本人との連絡、書類の準備、支援計画の作成、在留資格の申請など、自分たちだけでは到底できなかったと思います。今ではAさんが再び現場で活躍してくれていて、利用者の方々も本当に喜ばれています。今後も外国人スタッフの採用を続けるうえで、ぜひまた相談させていただきたいと思います。